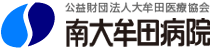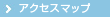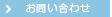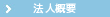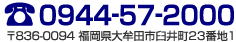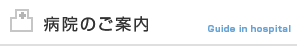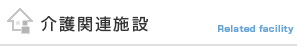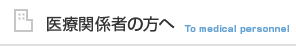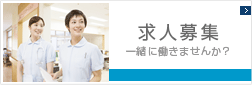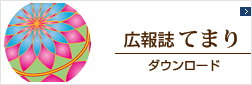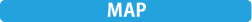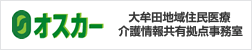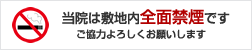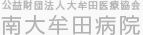広報誌Web版『知って防ごう食中毒』
みなさんこんにちは。日差しも強く、気温も高い日が増えてきました。湿気も多くなる季節ですので、みなさん熱中症に気を付けて過ごされてください過日、『知って防ごう食中毒』の健康教室が開かれたので紹介していきます。
はじめに【食中毒とは?】
食中毒とは、食中毒を起こす有害な細菌やウイルス、有毒な物質がついた食べ物を食べることによって、下痢や腹痛、発熱、吐き気などの症状が出る病気のことです。
食中毒の原因
食中毒の原因として、
- 細菌(カンピロバクター、腸管出血性大腸菌など・・・)
- ウイルス(ノロウイルスなど・・・)
- 自然毒(ふぐ、毒キノコなど・・・)
- 化学物質(ヒスタミン)
- 寄生虫(アニサキスなど・・・)
等あります。
その中でも、いくつかピックアップしてご紹介していきたいと思います。
カンピロバクター
特徴
- 家畜、家きん類の腸管に生息し、加熱していなかったり、加熱が不十分な食肉(特に鶏肉)やレバー等の臓器を食べることや、カンピロバクターに汚染された飲料水等を飲むことにより感染します。
- 乾燥にきわめて弱く、また通常の加熱処理で死滅する。
症状
- 潜伏期間は1~7日と長い(潜伏期間とは病原体に感染してから発症するまでの期間)
- 発熱、倦怠感、頭痛、吐き気、腹痛、下痢、血便等。
- 少ない菌量でも発症。
過去の原因食品
- 食品(特に鶏肉)、飲料水、生野菜など
- 潜伏期間も長いので、判明しないことも多い
対策
- 調理器具を十分消毒し、よく乾燥させる
- 肉との食品との接触を防ぐ
- 食肉、食鶏肉処理場での沿線管理、二次汚染防止を徹底する。
- 食肉は十分な加熱(65℃以上数分)を行う
ノロウイルス
特徴
- 原因食品の判明していないものが多く、その中には食品取扱者を介して汚染された食品が原因となっているケースが多いことが示唆されている。その原因としては貝類がある。
- 少量のウイルスでも発症する。アルコールや逆性石鹸では効果がない
(逆性石鹸→陽イオン界面活性剤の一種で、殺菌効果を持つ石鹸)
症状
- 潜伏期間は24時間~48時間
下痢、嘔吐、吐き気、腹痛、発熱は一般的に軽度(37℃~38℃)
過去の原因食品
- 原因食品としては特定されないケース、調理従事者からの時に感染を原因とする事例が多くを占める。特定された事例では、貝類、弁当、刺身、すし、サラダ、餅、菓子、サンドイッチなど
欧米ではベリーによる事例が注目されている。
対策
- 二枚貝は中心部まで十分に加熱する(85~90℃、90秒間以上)
- 野菜などの生鮮食品は十分に洗浄する。
- 手指をよく洗浄、消毒する
- 食品を取り扱う際は十分に注意し手洗いを徹底する
黄色ブドウ球菌
特徴
- 人や動物に常在する。毒素を生成する
- 毒素は100℃、30分の加熱でも無毒化されない。
症状
- 潜伏期間は1~5時間(平均3時間)
- 吐き気、嘔吐、腹痛、下痢
過去の原因食品
- 穀類とその加工品、乳製品、卵製品、食肉製品、魚肉ねり製品、和洋生菓子等
対策
- 手指の洗浄
- 調理器具の洗浄殺菌
- 手荒れや化膿巣のある人は、食品に直接触れない
- 防虫、防鼠対策は効率的
- 低温保存は有効
ウエルシュ菌
特徴
- 人や動物の腸管や土壌、下水に広く生息する。酸素のない所で増殖する菌で芽胞を作る。芽胞は100℃、1~6時間の加熱に耐える。食物と共に腸管に達したウエルシュ菌は毒素を作り、この毒素が食中毒を起こす。1事例あたりの患者数が多く、しばしば大規模の発生がある。
症状
- 潜伏期間は6~18時間(平均10時間)。
- 主症状は下痢と腹痛で、嘔吐や発熱はまれである。
過去の原因食品
- 多種多様の煮込み料理(カレー、煮魚、麵のつけ汁、野菜煮つけなど)
対策
- 清潔な調理を心掛け、調理後速やかに食べる。食品中での菌の増殖を 阻止するため、加工調理食品の冷却は速やかに行う
- 食品の保存する場合は、10℃以下かつ55℃以上を保つ
- 食品を再加熱する場合は十分加熱して増殖している菌を殺菌し早めに摂食する
- 加熱しても芽胞は死滅しないこともあるため加熱を過信しない
ボツリヌス菌
特徴
- 土壌中や河川、動物の腸管など自然界に広く生息する
- 酸素のない所で増殖し、熱にきわめて強い芽胞を作る
- 毒性の強い神経毒を作る。毒素の無毒化には、80℃で20分間の加熱を要する
症状
- 潜伏期間は8~36時間
- 吐き気、嘔吐、筋力低下、脱力感、便秘、神経症状
- 致死率は抗毒素療法の導入後、約30%から約4%に低下
過去の原因食品
- 缶詰、瓶詰、真空パック食品(辛子れんこん)
- レトルト類似食品、飯寿司(乳児ボツリヌス症:はちみつ)
対策
- 発生は少ないが、いったん発生すると重篤になる。
- 飯寿司による発生が多いので注意が必要
- 容器が膨張している缶詰や真空パック食品は食べない
- ボツリヌス中毒が疑われる場合、抗毒血清による治療を早期に開始する
レトルト食品と真空パックの違い
- レトルト食品は、中心温度120℃4分以上と、加圧加熱殺菌の条件が決められています。
高温高圧の条件下で腐敗や食中毒の原因になる菌を殺菌するためです。未開封の場合は常温保存が可能です。 - 真空パックなどの密封食品は味や食感を保つために高温高圧処理がされていません。殺菌レベルが低いために、開封前でも冷蔵庫保存が必須です。
| 開封前 | 開封後 | |
|---|---|---|
| レトルト食品 | 常温保存 | 要冷蔵 |
| 真空パック | 要冷蔵 | 要冷蔵 |
腸管出血性大腸菌
特徴
- 動物の腸管内に生息し、糞便等を介して食品、飲料水を汚染します。少量でも発病することがある。
症状
- 感染後平均4~8日間の潜伏期間
- 初期感冒症状のあと、激しい腹痛と大量の新鮮血を伴う血便。発熱は少ない。重症では溶結性尿毒性症候群を併発し、意識障害や死に至ることもある。
過去の原因食品
- 日本:井戸水、牛肉、牛レバー刺し、ユッケ、ハンバーグ、牛角切りステーキ、そば、ローストビーフ、鹿肉等
- 海外:ハンバーガー、ローストビーフ、ミートパイ、レタス、アルファルファ、ほうれん草、アップルジュース等
対策
- 食肉は中心部までよく加熱する(75℃1分以上)
- 野菜類はよく洗浄。
- と畜場の衛生管理、食肉店での二次汚染対策を十分に行う。
- 低温保存の徹底
食中毒予防の6つのポイント
- 食品の購入:新鮮なもの、消費期限を確認して購入する等
- 家庭での保存:持ち帰ったらすぐ冷蔵・冷凍庫に保存する等
- 下処理:手を洗う、きれいな調理器具を使う等
- 調理:手を洗う、十分に加熱する(75℃1分以上)
- 食事:手を洗う、室温に長く放置しない等
- 残った食品:きれいな器具容器で保存する、再加熱等
アニサキス
特徴
- 約2~3cmで白色の少し太い糸状の寄生虫
- アニサキス幼虫が寄生している魚介類
(サバ、イワシ、カツオ、サケ、イカ、サンマ、アジ等)
症状
- アニサキス幼虫が寄生する生鮮魚介類を食べた後、数~十時間後に激しいみぞおちの痛み、悪心、嘔吐。→急性胃アニサキス症
- 十数時間後以降に、激しい下腹部痛、腹膜炎症状等。→急性腸アニサキス症
予防方法
- 新鮮な魚を選び、速やかに内臓を取り除く。
※アニサキス幼虫は鮮度が落ちると、内臓から筋肉に移動することが知られている - 魚の内臓を生で提供しない。
- 目視で確認して、アニサキス幼虫を除去する。
- 冷凍 (-20℃で24時間以上)
- 加熱する(60℃で1分、70℃以上)
※一般的な料理で使う食酢の処理、塩漬け、しょうゆやワサビではアニサキスの幼虫は死滅しない。
正しい手洗いを!
予防の基本として、食事前はもちろん、調理中の生の肉・魚介類・卵を触った後、トイレに行ったりゴミ箱に触ったり、ペットに触れた後には忘れずに手を洗いましょう
- 流水で洗う。
- せっけん液を手に取る
- よく泡立てる
- 手の平を洗う
- 手の甲を洗う
- 指の間を洗う
- 指の間を洗う
- 親指を洗う
- 手首を洗う
- 流水で洗い流す
- よく水気をふき取る
- アルコールで消毒
食中毒かな?と思ったら
食中毒の症状が出たらどうすればいい?
下痢や嘔吐をしたら、しっかりと水分を取りましょう
自分で勝手に判断して薬を飲むのはやめて、まず医師に診てもらいましょう。
食べたもの、食品の包装、店のレシート、吐いたものが残っていたら保管しましょう。原因を調べたりするのに使います。
食中毒の症状が重くなりやすい人は?
乳幼児や高齢者の方
妊娠中の方
肺臓疾患、癌、糖尿病の治療を受けている方
錠剤を飲む必要のある貧血の方
胃腸の手術を受けた、胃酸が少ない等、胃腸に問題のある方
ステロイドが入っている薬を飲んでいる、HIVに感染している等、免疫力が落ちている方
家族にうつさないようにするには、どうすればいい?
- うつらない・うつさないために、特に調理の前、食事の前、トイレの後、吐いたものに触った後には、よく手を洗いましょう。
- 食中毒の感染した恐れのある人は調理を控えましょう。
- 食中毒に感染した恐れのある人が使用した食器や調理器具は、洗剤で洗うだけでなく、煮沸消毒しましょう。
- 食中毒に感染した恐れのある人は下着、衣類は別に選択しましょう。
- 入浴も家族の後に入るようにしましょう。湯船のお湯も毎日かえましょう。
- また、家族が食中毒にかかったら、お風呂の残り湯を洗濯に使うのはやめましょう。
まとめ
「健康のために食生活に気をつけたい」、「食中毒が怖いけどどうやったら防げるの!?」などと日々感じている方もいらっしゃると思います。
健全な食生活を送るうえで、食品の安全性について正しい知識をもち、取り扱うことはとても大切なことです。
「そんなの難しいし面倒だ」と思う人もいるでしょう。
でも、これまでの習慣を少し見直し、ほんのちょっと工夫するだけでより健全な食生活に近づけると私たちは考えます。
引用文献
- 内閣府 食品安全委員会食中毒予防のポイント
- 厚生労働省 食中毒統計資料
- 厚生労働省 ノロウイルス食中毒予防対策リーフレット
- 厚生労働省 アニサキスによる食中毒を予防しましょう
- 農林水産省 HP食中毒かなと思ったら
- 農林水産省 安全で健やかな食生活を送るために


最後に
今回の、「知って防ごう食中毒」はいかがでしたでしょうか?
暑い日が続いていますが、水分補給をしっかりし熱中症に気をつけて過ごされてくださいね
大牟田地域住民医療・介護情報共有拠点事務室OSKER
大牟田の医療・介護施設情報を掲載しています。どなたでも好きな写真を投稿できるギャラリーを製作いたしましたのでご紹介いたします。
次号は「こむら返りの原因と対処法。夏バテ予防健康体操。」をご紹介します。